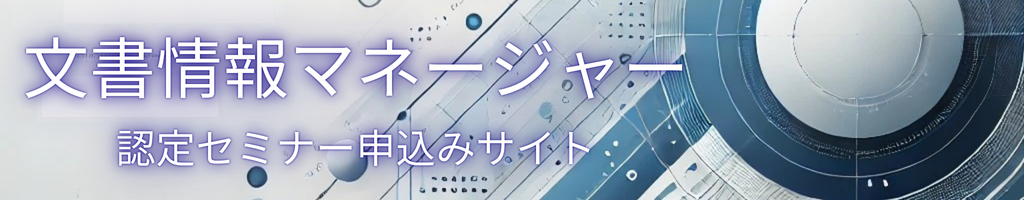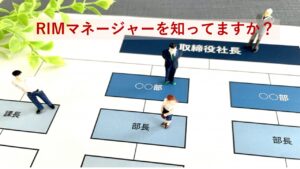名古屋市バス 運行記録改ざん発覚! なぜ改ざんができてしまうのか?
はじめに
名古屋市の広沢一郎市長は2月17日の定例記者会見で、名古屋市営バスの運行記録の不正に関する報道について説明を行いました。この会見によれば、名古屋市営バスの猪高営業所において、運転手の休息時間を国の基準で定められた9時間に合わせるために、バスの遅れを別の日に付け替えるなどの運行記録の改ざんが行われていたと説明しました。
運行記録は改ざんされたのか?
2月17日のTBSニュースの配信動画(YouTube)によると、昨年関係者から入手した文書と、情報公開請求によって入手した文書に差異がありました。動画の内容から、この文書が「乗務指示書兼点呼簿」であると読み取れました。
具体的には、10月3日の文書では「渋滞があった」と記載されているのに対し、情報公開文書では渋滞の記載が二重線(取消し線)で消されていました。また、10月15日の文書では6.8kmの距離を6分で走行したことになっているのに、情報公開文書では19分で走行したことになっていました。
このような修正は、運転手の休息時間を国の基準である9時間に合わせるために、運行記録を調整、または書き換えたものと考えられます。そもそも、記録が適正に作成されていなかったものや、後で訂正されたものもあり、すべてが改ざんとは言えないものの、不正な記録が存在したことは間違いありません。
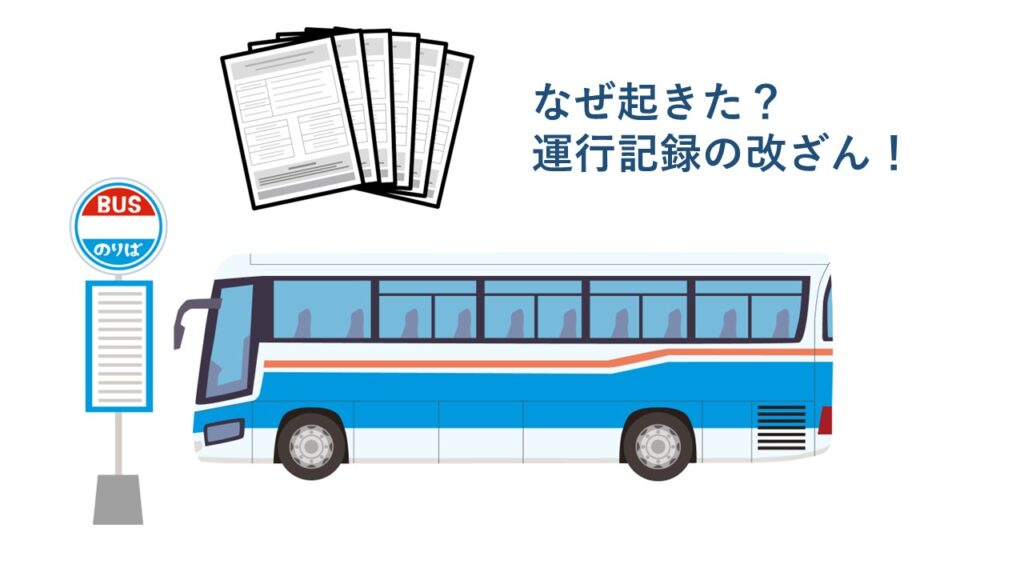
もう紙文書での記録保存はやめませんか?
各社報道の映像を確認すると、この運行記録(乗務指示書兼点呼簿)はパソコンで作成された文書を紙に印刷し、追加のコメントや押印を加えたものでした。紙文書の場合、事務所で保管している限り、悪意があれば容易に訂正や差し替えが可能です。
今回、営業所の助役が事実と異なる文書を作成したことに対して責任を問う声もありますが、文書情報マネジメントの観点から考えると、少なくとも電子文書として保存し、改ざんや隠滅を防ぐ仕組みを導入すべきだったと言えます。
紙文書での記録保存は「性善説」に基づいた運用です。しかし、人間は必ずしも強いものではなく、むしろ弱いものです。「性弱説」に立てば、出来心や追い詰められた状況で不正に手を染めることもありえます。そのため、仮に不正をしようと考えたとしても、容易に改ざんや隠滅ができない仕組みを整えることが重要です。
現実的な運用設計ができていなかったのでは?
10分程度の遅れが生じるたびに、計画していたシフト体制を変更し、予備の人員を緊急に配置しなければならないというシフト設計が妥当だったのか、疑問が残ります。このような計画は現実的ではなく、むしろ現場に過度なプレッシャーを与えていることになり、問題ではないでしょうか。
今回、不正に手を染めたのは営業所の助役でしたが、このプレッシャーが運転手に向けられた場合、大事故につながる可能性があります。
JR西日本・尼崎事故の教訓を活かしてほしい
2005年4月に発生したJR西日本・尼崎の脱線事故を思い出してください。JR西日本が定時運行を優先するあまり、運転手に過度なプレッシャーをかけたことが事故の原因となりました。
バス運行においても、運転手に過度なプレッシャーをかけると、スピード超過や安全軽視につながり、大事故を引き起こす可能性があります。このような事態を何としても防ぐべきです。
PDCAを回すことが大切
文書情報マネジメントの観点から見れば、「9時間の休息時間を記録上だけ確保する」のではなく、どうしても確保できなかった場合は、その記録を正しく残し、市として適切な対策を検討することが必要です。
不正を防ぐためには、PDCA(Plan-Do-Check-Act)サイクルを適切に回し、継続的に改善を行うことが求められます。これにより、不適切な運行管理を是正し、持続可能なバス運行体制を確立できるはずです。
まとめ
今回の問題は、単なる個人の不正行為ではなく、組織全体の運用体制や管理手法に起因するものです。文書情報マネジメントの観点からも、より適切な記録保存と管理方法を導入することで、同様の問題を未然に防ぐことが可能となるでしょう。