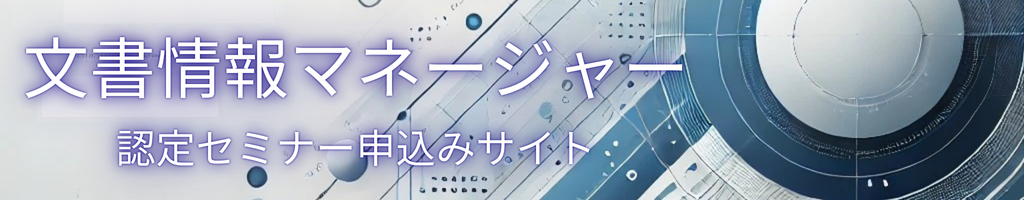ETC大規模障害発生 ~マニュアルの整備が対策?~
▶ はじめに
2025年4月6日に発生したNEXCO中日本のETCシステム障害により、東名、新東名、中央道など11路線の30カ所以上の料金所でETCが利用不能となりました。これにより、係員が対応する一般レーンでの通行処理が必要となり、出口での渋滞が発生しました。特に名古屋ICや岡崎IC、新城ICなど主要なインターチェンジで影響が大きかったと報じられています。
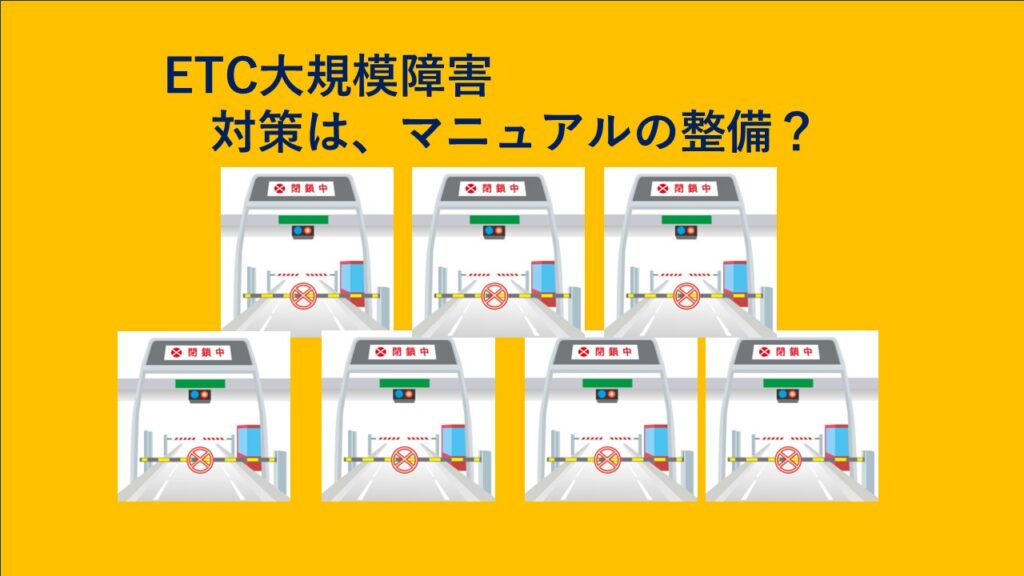
▶高まる非難の声
システムには障害がつきものです。しかしながら、今回は非難の声が大きくなっています。その理由は3つあります。
1.原因の特定と説明の不備
当初、障害の原因は4月5日に実施された深夜割引制度の見直しに伴うシステム改修とされていましたが、後に無関係と判明しました。その後も根本的な原因は不明のままです。
2.対応の遅れと混乱
障害発生から約12時間後に一部料金所でゲートを開放し、後日精算の対応を取りましたが、初動の遅れが渋滞や混乱を拡大させたと指摘されています。
3.利用者への負担と不透明な請求
障害中にETC専用レーンを通行した約92万件に対し、NEXCO中日本は後日精算を求めていますが、利用者からは「支払い義務があるのか」「手続きが煩雑」といった不満が噴出しています。
▶国交省が指示した対策は
これに対し、国土交通省の中野洋昌大臣は、NEXCO中日本に以下の3点を指示したとのことです。
1.原因究明と当面の対策の取りまとめ(4月中)
2.再発防止策と危機対応マニュアルの作成(6月中)
3.有識者を交えた検討委員会の設置
▶危機対応マニュアルの作成が再発防止の切り札か?
NEXCO中日本には、危機対応マニュアルがなかったのではなく、大規模な広域障害への対応が想定されていなかったことが明らかになっています。「大規模な広域障害への対応が抜けていたから、その対策をしろ!」では、再発防止になっていないと思われます。
▶文書情報マネジメント視点から気になること
文書情報マネジメントの視点からは以下のことが気になります。
1.大規模な広域障害への対応を想定外とした意志決定プロセス並びにその記録
危機対応マニュアル自体は存在しているが、その作成過程での意志決定プロセスとその記録を残しているか。残っていれば、不足していた点や間違った箇所がわかるので、将来の参考となるが、残っていないとしたら、そもそも、そこに組織文化、組織風土の問題があることになります。
2.フェイルセーフの設計思想でのシステム化
今回のETCシステム障害の原因は、広域管理システムから地域管理システムへの「ETC課金に必要なデータ」の自動定時配信時にデータ破損が生じたためとされています。情報処理試験でも基本事項として「フェイルセーフ」という考え方があります。NEXCOにおける“セーフ”とは「料金を取り損ねないこと」だったとすれば、そのためには通行を止めるべきだったのではないでしょうか。
ちなみに、NEXCO中日本の基本姿勢は次の6つです。
①お客さま起点で考える
②現場に立って考え行動する
③経験と知見を結集する
④効率性を追求する
⑤時代に即して進化し続ける
⑥社会の課題と向き合う
一番に掲げられている「お客さま起点で考える」と、今回のETCシステムの設計思想は相いれないように思われます。システムの中にも企業理念をいかにしみ込ませるかということが、今後の重点的な見直しポイントではないでしょうか。
3.何故、エスカレーションができなかったか
全てのことが想定内でマニュアル化できていれば、それに越したことはありませんが、全知全能でない限りそのようなことは不可能です。ですので、大抵の組織では障害・事故の報告はその大きさにより、エスカレーションパスが設定され、一番大きい場合は、経営トップまで届くようになっています。そして、エスカレーションがあった場合には、迅速な判断と対応が求められます。
結果論からすると、ここに大きな課題があったと見受けられます。
4.まとめ
今回の障害は事故というべき状態になってしまいました。この事例を他山の石として、民間、官公庁自治体を問わず、そんなことは発生しない、想定外にしておこうとしたインシデントについて、判断は正しいのか、見直す必要があるのではないでしょうか。